こんちはキャリーライフ中川です。
評価額が高い土地の落とし穴と実家の相続対策
土地を持っていれば資産。
けれど、「評価額が高い=安心」とは限りません。
固定資産税や相続税の負担が重くなる一方、
実際には売れにくく、
管理費だけがかかる…
そんな“負動産”化のリスクも現実のものです。
評価額が高い土地ほど注意したい点と、
実家や相続における土地の取り扱いについて、
事前に知っておくべきポイントをお伝えします。
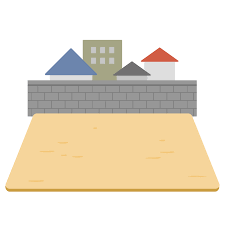
目次構成
1|評価額が高い土地=資産とは限らない
・1-1:高評価=高負担という現実
・1-2:「売れない土地」になる理由
2|相続税が発生しやすい評価ゾーンとは?
・2-1:都市部・路線価が高いエリアの盲点
・2-2:分けにくい土地・利用しにくい土地の問題
3|実家の土地をどう扱う?
・3-1:親が元気なうちにできる「見える化」
・3-2:実家を残す・手放すの判断基準
4|評価額と“空き家リスク”の関係
・4-1:評価が高いのに使われない家の共通点
・4-2:「負動産」になる前にしておきたい行動
1-1:高評価=高負担という現実
評価額が高い土地は、
一見「資産価値が高い=安心」と思われがちです。
固定資産税や都市計画税などの税負担が重くなり、
年に数十万円の維持費がかかるケースも少なくありません。
さらに、評価額に連動して相続税額も増えるため、
「相続しても手放すしかない」という事例も多発しています。
1-2:「売れない土地」になる理由
評価額は高いのに、
実際は売れない・売りにくい土地も存在します。
その理由は、
・再建築不可
・敷地延長(旗竿地)
・隣地との共有トラブル
固定資産税評価額や路線価は、
個別事情まで反映していないため、
市場価値(実勢価格)と乖離していることも多いのが実態です。
実用性や権利関係のチェックも欠かせません。
2-1:都市部・路線価が高いエリアの盲点
都心部や駅近エリアにある実家などは、
路線価が非常に高く設定されていることが多く、
相続時には思わぬ税負担が発生する可能性があります。
たとえば、
1㎡あたりの路線価が30万円の土地(100㎡)であれば、
それだけで評価額は3,000万円。
相続人が複数いても、物理的に分割できない土地では、
売却か納税資金の確保が避けられません。
2-2:分けにくい土地・利用しにくい土地の問題
相続においてトラブルになりやすいのが、
・形状が分割しにくい土地
・誰か1人が住み続ける場合の公平性
・商業地にあるが実際は古家付きで活用できない
評価額だけを基にした資産分割では納得が得られず、
遺産分割協議の長期化や兄弟間トラブルの原因になります。
不動産は「お金に見えるが、平等に分けにくい」
性質があるため、事前の備えが欠かせません。
親が元気なうちにできる「見える化」
親が元気なうちに、
所有する土地の評価と状況を“見える化”しておくことが重要です。
・評価額と実勢価格の比較
・再建築の可否
・土地利用の履歴と登記状況
3-2:実家を残す・手放すの判断基準
実家を「残すべきか、手放すべきか」は、
感情と経済のバランスを見極める必要があります。
・思い出や親の意志は尊重したい
・しかし管理・税金・修繕の負担は子世代にのしかかる
・誰も住まない場合、5年後には空き家リスクが高まる
「相続したけど使わず、放置して後悔した」という声も多いため、
元気なうちに家族での話し合いが不可欠です。
4-1:評価が高いのに使われない家の共通点
実際に空き家予備軍として増えているのが、
・市街地にある高評価の住宅地
・親が施設入居で不在になった実家
・相続後、誰も住まずに放置されている家
評価額が高いから売れるとは限らず、
高評価ゆえに税・管理の負担が重く、
放置されるという矛盾が起きています。
いわゆる「隠れ負動産」化の第一歩です。
4-2:「負動産」になる前にしておきたい行動
大切なのは、“評価が高い=価値がある”と安心せず、
維持・活用・処分の選択肢を明確に持っておくことです。
・利用予定がなければ、早期売却・賃貸・管理委託も検討
・親との対話で、意志を確認しておく
・「実家じまいノート」に記録して、家族で共有
こうした備えが、資産を負担に変えないための第一歩になります。
