こんにちはキャリーライフ中川です。
「人生100年」と言われる時代
老後の暮らしは誰にとっても“他人事ではない問題”になっています。
住宅ローン、住み替え、介護、孤独、空き家。
これまでの常識が通じない今、長寿時代をどう生きるか、
どこで暮らすかが重要になっています。
「住まい」に焦点を当てて、
人生100年時代に備えるための現実的な戦略を4つの視点から整理します。
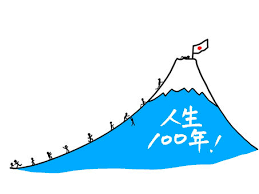
目次
1|老後の生活費と住宅費のリアル
・1-1:老後にかかる生活費はいくら?
・1-2:持ち家・賃貸で変わる住宅コスト
2|住み替えの選択肢とタイミング
・2-1:定年後に多い住み替え理由とは?
・2-2:住み替えの最適な年齢と準備
3|親の家・実家の“見直し”が重要に
・3-1:空き家になる前に考えるべきこと
・3-2:実家を“住み継ぐ”か“手放す”か
4|これからの住まいは“自立+共助”
・4-1:シニア向け住宅や多世代同居の可能性
・4-2:地域とのつながりが“安心”をつくる
1-1:老後にかかる生活費はいくら?
総務省「家計調査報告(高齢夫婦無職世帯)」によれば、
月の平均支出は約24.5万円。
一方、年金収入は平均20.6万円とされており、
毎月約4万円の赤字が続く計算になります。
年間で約50万円の不足となり、
退職後30年間で約1,500万円の備えが必要とされます。
住まいに関わる支出(家賃、修繕、固定資産税)も
大きく影響するため、住宅費の見直しは老後設計のカギです。
1-2:持ち家・賃貸で変わる住宅コスト
一般的に「持ち家は老後に有利」と言われますが、
それはローン完済済みで修繕費や固定資産税に備えがある場合に限ります。
一戸建ての修繕費は築30年で平均500〜700万円かかると言われ、
マンションでも大規模修繕が10〜15年ごとに発生します。
一方、賃貸は住み替えや介護施設移行の柔軟性がありますが、
家賃負担が一生続くため、年金生活とのバランスが重要です。
2-1:定年後に多い住み替え理由とは?
定年後の住み替え理由として多いのは、
1位:バリアフリーや生活動線の見直し
2位:子どもの独立後の住まい縮小
3位:介護・通院に便利な立地への移動
国交省の調査では、60代の住み替え希望者のうち
約63%が「現在の家が将来に合わない」と回答しています。
老後のライフスタイル変化を見越した住み替えは、
早めの準備が安心につながります。
2-2:住み替えの最適な年齢と準備
「住み替えは70代でもいい」と思われがちですが、
実際に住み替えを決断・実行しているのは
60代前半が最も多いです。
体力・判断力・資金力のあるうちに決めることで、
後悔を減らすことができます。
特に実家の相続や親の介護が視野に入る世代(50〜60代)には、
ダブルの住まい見直しタイミングが重なりやすく、注意が必要です。
3-1:空き家になる前に考えるべきこと
実家を放置したまま高齢の親が施設に入所すると、
数年で空き家化が進行します。
現在、全国の空き家数は約900万戸、
う「その他の住宅」=放置空き家が350万戸以上(総務省)
相続後では対応が遅れることが多く、
親が元気なうちの相談・方向性確認が重要です。
3-2:実家を“住み継ぐ”か“手放す”か
親の家を引き継ぐかどうかの判断には、
・老朽度合い
・立地や流通性
・将来の資産価値
・維持費用
といった観点が必要です。
住み継ぐ場合も、バリアフリー改修や耐震補強を要するケースが多く、
一方で手放すなら、
早期売却や利活用の検討で“負動産”リスクを避けられます。
4-1:シニア向け住宅や多世代同居の可能性
高齢者単身世帯が増加する一方で、
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や
多世代同居型住宅などの選択肢も注目されています。
サ高住は2023年時点で約28万戸まで供給され、
柔軟な見守りと賃貸の仕組みが好まれています。
親子での近居や敷地内同居など、
新しい住まい方の可能性も広がりつつあります。
4-2:地域とのつながりが“安心”をつくる
人生100年時代の住まいは、
「建物」だけでなく「人とのつながり」も重要です。
高齢期の生活満足度は、
社会参加や近隣との関係性の有無で大きく差が出ます(内閣府調査)
地域サロンや自治体の見守り活動、
小規模多機能住宅との連携など、
孤立しない暮らしの仕組みを意識することが、
安心の老後につながります。
つづく
