こんちはキャリーライフ中川です。
日本の人口は2008年をピークに減少へ転じ、
総務省の推計では
2023年から2050年までに約3割減る見通しです。
人口減少は住宅市場にも直結し、
空き家増加や不動産価格の二極化を加速させています。
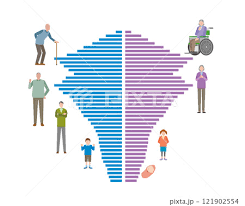
目次
1|人口減少の現状と予測
・1-1:全国的な人口減少スピード
・1-2:地域別の人口動態の差
2|住宅市場に与える影響
・2-1:需要減少による価格下落
・2-2:都市と地方の二極化
3|空き家が増える理由
・3-1:相続後の放置と管理負担
・3-2:売却が難しい立地条件
4|今後の予測と備え
・4-1:2040年までの空き家率予測
・4-2:今からできる資産価値維持策
1-1:全国的な人口減少スピード
総務省の日本の将来推計人口によると、
日本の人口は2023年の1億2,240万人から
2050年には8,700万人まで減少すると予測されています。
27年間で約29%減という急激な減少です。
1-2:地域別の人口動態の差
人口減少は全国一律ではなく、
東京都など一部の都市部では緩やかな減少、
地方の過疎地域では年間2〜3%減という急減も見られます。
この地域差が住宅需要の格差を拡大させ、
地価や賃料にも影響を及ぼします。
同じ県内でも売れる地域と売れない地域が
はっきり分かれるようになっています。
2-1:需要減少による価格下落
人口減少は住宅需要を直接的に減らします。
需要が減れば、
特に中古住宅や土地は買い手がつきにくくなり、
価格は下落傾向になります。
国土交通省のデータでも、
人口減少率の高い地域は地価が年1〜2%下落するケースが多く、
長期的には資産価値の目減りが避けられません。
2-2:都市と地方の二極化
都市部では依然として住宅需要が高く、
新築・中古ともに価格は高止まりしています。
地方では、空き家や売地が増加しても買い手が現れず、
価格は下落傾向です。
二極化は今後さらに広がり、
「資産になる家」と「負動産化する家」の差が明確になります。
3-1:相続後の放置と管理負担
空き家の多くは相続がきっかけで発生します。
所有者が遠方に住んでいる場合、
管理や活用が難しく、結果として放置されやすくなります。
3-2:売却が難しい立地条件
需要の少ない地域や、
再建築不可・接道条件を満たさない土地は、売却が困難です。
特に山間部や過疎地では、
無償譲渡しても引き取り手がないケースが増えています。
空き家率の上昇に拍車をかけています。
4-1:2040年までの空き家率予測
野村総合研究所の推計では、
2040年の全国空き家率は約40%に達すると予測されています。
全国の住宅の2軒に1軒近くが空き家になる計算で、
地域インフラや防犯、防災にも深刻な
影響を与える可能性があります。
4-2:今からできる資産価値維持策
人口減少社会で住宅資産を守るには、
早期の活用・売却・賃貸化の判断が重要です。
省エネ改修や耐震補強など、価
値を維持するためのリフォームも有効です。
将来どうするかを家族で話し合い、
計画的に行動することで、負動産化を防ぐことができます。
つづく
