こんちはキャリーライフ中川です。
高齢者が快適に暮らすためには、
住まいの温度や湿度の管理が欠かせません。
特に近年の研究では、
室内環境の乱れが認知症リスクを高める可能性が指摘されています。
夏の熱中症や冬の低体温だけでなく、
慢性的なストレスや睡眠障害を招く点も見逃せません。
、温度・湿度と認知症の関係をデータとともに整理し、
家庭でできる予防の工夫をお伝えします。
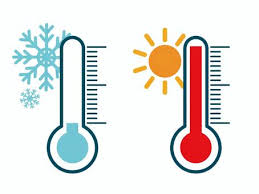
【目次】
- 温度と認知症リスクの関係
・1-1 夏冬の温度差がもたらす負担
・1-2 睡眠と体温調整の重要性
- 湿度が影響する健康リスク
・2-1 カビ・ダニと認知症の関係
・2-2 脱水と脳機能の低下
- 実際のデータで見る高齢者のリスク
・3-1 季節ごとの救急搬送件数の比較
・3-2 認知症患者数と住環境要因の分析
- 家庭でできる温度・湿度管理術
・4-1 空調・換気・加湿器の上手な活用法
・4-2 住まいを「健康住宅」に変える工夫
1-1 夏冬の温度差がもたらす負担
高齢者は体温調節機能が低下し、
外気温の変化に弱い傾向があります。
冬は低温環境は血圧上昇や脳血管疾患のリスクを高め、
認知症の発症要因になると指摘されています。
環境省の調査では、
冬季に室温が18度未満の住居に暮らす高齢者は、
そうでない人に比べて健康リスクが
約1.4倍高いという結果が出ています。
1-2 睡眠と体温調整の重要性
認知症予防には睡眠の質が欠かせません。
夜間の室温が高すぎたり低すぎたりすると
深い睡眠が得られず、脳の老廃物を処理する働きが滞ります。
特に夏は室温が30度を超える夜間熱中症、
冬は10度以下の冷え込みが睡眠の質を
大きく下げるため、適切なエアコン使用が重要です。
2-1 カビ・ダニと認知症の関係
湿度が高すぎるとカビやダニが繁殖し、
アレルギーや呼吸器疾患の原因となります。
慢性的な炎症を引き起こし、
脳の機能低下につながる可能性が報告されています。
厚労省の調査では、
室内湿度が70%を超える環境で暮らす高齢者は、
呼吸器系疾患の発症率が1.3倍高いというデータがあります。
2-2 脱水と脳機能の低下
湿度が低すぎると脱水リスクが高まります。
特に冬場は自覚のないまま脱水が進み、
血液粘度の上昇から脳梗塞を招くことも。
軽度脱水状態でも注意力や記憶力の低下が確認されており、
認知症の症状を悪化させる要因になり得ます。
3-1 データで見る季節ごとの高齢者のリスク
総務省消防庁の統計によれば、
熱中症による救急搬送者数は毎年約7万人、
そのうち約50%が65歳以上の高齢者です。
特に梅雨明けから夏本番にかけて急増し、
冬の低体温による救急搬送件数と比べても
2倍以上の差があることが分かっています。
3-2 認知症患者数と住環境要因の分析
国立長寿医療研究センターの研究では、
住宅の断熱性能が低い世帯は
高齢者の認知症発症率が1.2倍高いと報告されています。
住環境と脳の健康は密接に関わっており、
温度・湿度管理は予防の基本的アプローチとして位置づけられます。
4-1 空調・換気・加湿器の上手な活用法
エアコンは28度の冷房、
冬は20度の暖房を目安に使用すると
快適性と省エネを両立できます。
換気は1時間に1回を目安にし、
空気の淀みを防ぐことが大切です。
冬場の加湿は40〜60%を保つことが理想で、
インフルエンザ予防にも効果的です。
住環境を整えることがで
認知症予防の生活基盤づくりにもつながります。
つづく
