こんにちはキャリーライフ中川です。
家を建てる人が減る時代へ
厚生労働省が9月に発表した速報値
2025年1〜6月の出生数は33万9280人
(前年同期比−3.1%)
上半期としては過去最低を更新しました。
日本の出生数は2015年以降、10年連続で減少。
少子化が加速する中、
家族の形・家の持ち方も変化しています。
かつて結婚したら家を建てるが当たり前だった時代から、
今は家を建てるかどうかを迷う時代へ。
出産数の減少は、住宅市場の構造変革となっております。
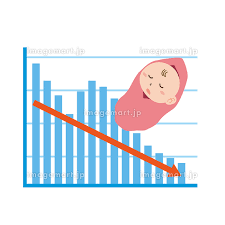
【目次】
1-1 出産数減少が止まらない現実
1-2 若年層の“家を持たない選択”
2-1 住宅市場を支える世代構造の変化
2-2 これからの“家族と住まい”の関係
1-1 出産数減少が止まらない現実
厚労省統計によると、
2024年の出生数は72万809人で過去最少。
ピークだった1973年(209万人)と比べると、
50年で3分の1以下になりました。
出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの数)
1.20に低下。
政府の掲げる「出生率1.6回復」
目標には遠く及びません。
住宅市場に直接的な影響を及ぼします。
世帯数の増加が止まり、
住宅需要の中心が家を建てるよりも
家を引き継ぐ方向へ移りつつあるのです。
1-2 若年層の“家を持たない選択”
国土交通省「住宅市場動向調査(2024)」によると、
30代で住宅を購入した人の割合
過去10年で約25%減少。
一方、賃貸を選ぶ割合は
同期間で1.4倍に増加しました。
理由として挙げられるのは、
・結婚・出産のタイミングが遅れている
・将来の不安からローンを避ける
・親世代の家を引き継ぐ見通しがある
住宅の新築需要が構造的に減っているのです。
出産数の減少は、単に人口の問題ではなく、
家の流通構造が変わる“入口でもあります。
2-1 住宅市場を支える世代構造の変化
国交省の推計によれば、
2035年には全世帯の約4割が単身世帯
65歳以上が世帯主の家は全体の35%超。
家を建てる世代よりも、
家を手放す世代が増える構図です。
住宅市場の需要は、新築からリフォーム
空き家活用・相続整理へと移行中。
建てることよりも、どう残すか・どう活かすか
中心テーマになりつつあります。
住宅産業は拡大を前提としてきましたが、
これからは維持と循環が主軸となります。
2-2 これからの“家族と住まい”の関係
出産数の減少は、家族構成だけでなく、
家の広さ・立地・機能にも変化をもたらします。
子ども部屋を前提としない間取り、
働く世代が親と近居する二世帯のゆるやかな共生、
地域内で住み替える循環型住宅など。
住み続ける家から暮らしに合わせて変える家へ。
少子化は住宅業界にとって逆風ですが、
柔軟な住まい方が求められる転換点でもあります。
出産数の減少は、住宅市場にとって
長期的な構造変化のサインです。
「建てる時代」から「活かす時代」へ。
子どもが減っても、家の価値を守る方法はあります。
家を次世代につなぐこと、地域の中で循環させること。
つづく
