こんちはキャリーライフ中川です。
近年、犬や猫などのペットが高齢者の
心身の健康と認知症予防に与える効果が注目されています。
ペットと暮らすことで
・生活リズムの維持
・交流の促進
・ストレス軽減
孤立感を和らげることも報告されています。
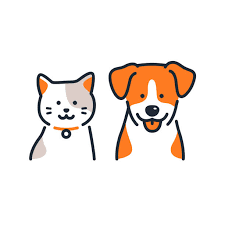
【目次】
- ペットと高齢者の暮らしの現状
・1-1 高齢者世帯におけるペット飼育率
・1-2 ペットがもたらす心理的な効果
- ペットと認知症予防の関係
・2-1 生活リズムの維持と脳の活性化
・2-2 交流・社会参加の広がり
- 健康への具体的メリット
・3-1 ストレス軽減と血圧への影響
・3-2 運動量の増加と体力維持
- ペットと暮らす上での注意点
・4-1 飼育の負担と現実的な選択
・4-2 ペットを通じた「家じまい」との関わり
1-1 高齢者世帯におけるペット飼育率
ペットフード協会の調査によれば、
2023年時点で犬猫の飼育頭数は
約1,500万頭と推計されています。
高齢者世帯でも全体の約15%がペットを飼っており、
単身世帯や夫婦のみ世帯では増加傾向にあります。
特に都市部では小型犬や猫を選ぶケースが多く、
生活空間に合わせた飼育スタイルが広がっています。
孤独を和らげる重要な存在になっており、
家族同様の役割を担っているのが現状です。
1-2 ペットがもたらす心理的な効果
心理学の研究では、犬や猫と触れ合うことで
オキシトシンと呼ばれるホルモンが分泌され、
安心感や幸福感が高まるとされています。
ペットを飼う高齢者は「生きがいを感じる」と
答える割合が70%を超えており、
心の支えとしての存在が強調されています。
2-1 ペットと認知症予防の関係
生活リズムの維持と脳の活性化
毎日の生活リズムを安定させる効果があります。
犬の散歩や食事の世話は時間を意識させ、
規則正しい生活を促します。
認知症予防の観点でも重要で、
国立長寿医療研究センターの調査によれば
毎日同じ時間に活動する習慣がある人
は認知症発症率が約30%低いと報告されています。
2-2 交流・社会参加の広がり
犬の散歩を通じて近所の人と挨拶を交わす、
動物病院やペットサロンで会話が生まれるなど、
自然な社会参加が促されます。
高齢者の社会的孤立は認知症リスクを
約2倍に高めるとされており、
ペットが交流の架け橋となることは大きな意味を持ちます。
3-1 ストレス軽減と血圧への影響
米国心臓協会の研究によると、
犬や猫をなでることで血圧が下がり、
ストレスホルモンであるコルチゾールが
減少することが確認されています。
精神的安定は認知機能の維持にもつながり、
生活の質を大きく向上させます。
3-2 運動量の増加と体力維持
犬を飼っている高齢者は、
散歩によって日常的に運動量が増える傾向があります。
週に150分以上の中等度運動が推奨されていますが、
犬の散歩をしている人は
この基準を満たしやすいことが調査で示されています。
4-1 ペットと暮らす上での注意点
飼育の負担と現実的な選択
ペットの飼育には経済的・体力的な負担も伴います。
無理のない範囲で飼育するために、
シェア型ペットサービスや一時預かり制度の活用も選択肢
ペットを家族として迎えることは喜びですが、
最後まで責任を持つことが前提です
ペットの行き先をどう確保するかも重要な視点になります。
近年では「ペット信託」という制度もあり、
飼い主に万一のことがあった場合でも、
信頼できる人や団体に飼育を託せる仕組みが広がっています。
ペットと暮らすことは、
高齢者にとって単なる癒しを超え、
生活リズムの維持・社会参加・健康維持
多面的なメリットをもたらします。
つづく
