こんちはキャリーライフ中川です。
承継問題から考える“じまい”の共通点
「家じまい」と「墓じまい」
一見別のテーマのようですが、
どちらも承継者がいないと負動産となり
家族に負担を残す点で共通しています。
日本では少子高齢化が進み、
実家もお墓も「継ぐ人がいない」という現実が広がっています。
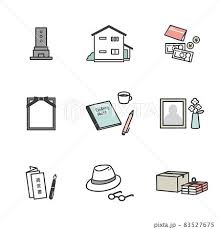
【目次】
1-1 承継者不在が生む“負動産”
1-2 管理費や維持費の負担増
2-1 お墓を放置した場合のトラブル
2-2 実家を放置した場合のリスク
3-1 少子高齢化と都市集中の影響
3-2 相続をめぐる意識の変化
4-1 墓じまい・家じまいを早めに検討する意義
4-2 「見える化」と家族対話の重要性
1-1 承継者不在が生む“負動産”
お墓と実家はいずれも
次の世代が引き継ぐことを前提に成り立ってきました。
子ども世代が遠方に住む・子どもがいないなど
承継者不在の家庭が増え、
資産が“負動産”へと変わる現実が広がっています。
お墓は無縁墓に、実家は空き家になり、
残された家族が困るケースは少なくありません。
1-2 管理費や維持費の負担増
お墓には年間数千円〜数万円の管理費、
実家には固定資産税や修繕費が発生します。
総務省調査によると
空き家の維持管理費は年間約20万円にのぼり、
墓地でも管理費未納による撤去件数が増加傾向です。
所有しているだけで費用がかかる構造が共通しており、
承継者にとっては重い負担となります。
2-1 お墓を放置した場合のトラブル
管理費を支払わなければ「無縁墓」とみなされ、
撤去対象となることもあります。
墓石の劣化は倒壊や事故の危険を生み、
親族間で責任問題に発展することもあります。
放置されたお墓は供養の場であると同時に、
リスクの発生源にもなってしまうのです。
2-2 実家を放置した場合のリスク
実家を空き家にすると老朽化や倒壊リスクが高まります。
国交省によれば、
全国の空き家数は約900万戸、
うち約350万戸が放置空き家。
特定空家に指定されると固定資産税が
最大6倍になる可能性があり、経済的負担が急増します。
3-1 少子高齢化と都市集中の影響
地方の人口減少と都市部集中が進み、
実家やお墓を引き継ぐ人材が不足しています。
継がない・継げないが社会全体に広がり、
“じまい”を考える必要性が高まっているのです。
3-2 相続をめぐる意識の変化
司法統計では相続放棄件数が
10年で約1.7倍に増加しました。
親の家や墓は当然継ぐものという意識から
負担になるなら継がないという意識への変化が見られます。
家も墓も「放置するリスク」を避けたいと考える人が増えています。
4-1 墓じまい・家じまいを早めに検討する意義
承継が難しいと分かっている場合、
元気なうちに墓じまいや家じまいを検討することが、
家族の負担を大幅に減らす最善策です。
早期対応は費用・手続きの簡略化にもつながります。
4-2 「見える化」と家族対話の重要性
資産や維持費を「見える化」して
家族で共有することが不可欠です。
墓じまいでは永代供養や改葬、
家じまいでは売却・賃貸・リフォームといった選択肢があります。
大切なのは“家族で早めに話し合い、合意形成をすることです。
お墓と実家は違うようで、
実はどちらも承継者不在が“負動産化”を招く
という共通課題を抱えています。
少子高齢化の進展により、この問題は避けられません。
つづく
