こんにちはキャリーライフ中川です。
保険では守れないお金の管理法
生命保険や医療保険は万が一の
死亡や病気には備えられます。
判断力の低下には保険では備えられません。
厚生労働省によると、
2024年時点で認知症高齢者は約690万人、
高齢者の5人に1人が発症している計算です。
2040年には850万人に達すると推計されています。
認知症になると、銀行口座が凍結され、
保険金の請求や不動産の売却もできなくなる。
どう備えるかが、今求められています。
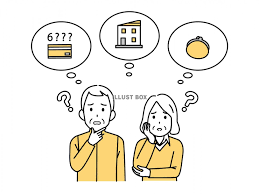
【目次】
1-1 判断力の低下が引き起こす「お金の凍結」問題
1-2 成年後見制度の限界
2-1 家族信託で“資産を動かせる”しくみをつくる
2-2 認知症リスク時代の“保険+信託”の新しい備え方
1-1 判断力の低下が引き起こす「お金の凍結」問題
認知症を発症すると、
契約や財産管理に関する意思能力が失われます。
その結果、本人名義の銀行口座は凍結され、
家族であっても自由にお金を
引き出すことができなくなります。
不動産の売却や修繕、生命保険の解約・請求も停止。
認知症になるとお金が動かせないのです。
特に実家を所有している高齢者の場合、
売却やリフォームの判断ができず、
空き家化するリスクが高まります。
相続前の段階で実家じまいが止まってしまうのも、
この凍結問題が背景にあります。
1-2 成年後見制度の限界
判断力を失った人のために成年後見制度があります。
実際の運用には課題が多いのが現実です。
後見人が選任されるまでに数か月を要し、
裁判所の監督下で自由にお金を使うことができません。
たとえば
・家の修繕
・孫の学費支援
原則として認められません。
さらに、年間報酬として2万〜6万円程度の
後見人費用が継続的に発生します。
一度後見が始まると、
本人が亡くなるまで解除できないため、
柔軟な財産管理には向かない制度といえます。
守ることはできても、活かすことはできない。
これが、成年後見制度の最大の弱点です。
2-1 家族信託で“資産を動かせる”しくみをつくる
注目されているのが家族信託(民事信託)です。
家族信託とは、親(委託者)が子ども(受託者)に
財産の管理・運用を任せる契約。
親が認知症になっても、子が信託契約に基づいて
銀行口座の管理・不動産の売却・修繕などを
続けられる仕組みです。
成年後見制度と違い裁判所の監督を受けずに、
家族の意向に沿った柔軟な運用が可能です。
実際に家族信託を活用している世帯では、
空き家の売却や相続税対策を
発症後も進められたという事例も増えています。
家族信託は資産を守るだけでなく
資産を動かす仕組みです。
2-2 認知症リスク時代の“保険+信託”の新しい備え方
生命保険が“亡くなった後”の備えなら、
家族信託は判断力を失う前後を支える仕組みです。
生命保険金の受取人を信託口座に指定する
信託連携型保険”も登場しています。
保険金を受け取った家族がすぐに使えるだけでなく、
信託契約に基づき介護費や生活費として
自動的に活用できるのです。
この仕組みは、保険では守れない期間を信託で補う
新しい備え方といえます。
将来の相続・介護・住まいの維持を見据え、
保険+信託の連携を検討することが、
これからの時代のスタンダードになるでしょう。
相続や介護の現場で混乱しないためには、
元気なうちに信託を組む
保険の受取先を見直すことが大切です。
判断できる今こそ、
未来のお金をデザインする。
認知症リスク時代を生き抜くための新しい選択です。
つづく
