こんにちはキャリーライフ中川です。
二世帯・相続前支援が増える背景とは
国土交通省の「住宅市場動向調査(令和5年度)」
住宅購入時に親や親族から援助を受けた人の割合は32.7%。
過去最高の数値であり、
10年前(2014年度)の23.4%から約9ポイント上昇しました。
相続や老後を見据えた“家族単位の資産戦略”があります。
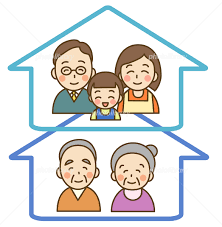
【目次】
1-1 親からの資金援助が増えている理由
1-2 援助のかたちは「贈与」から「共同設計」へ
2-1 二世帯・近居の増加とその目的
2-2 相続前支援
1-1 親からの資金援助が増えている理由
親世代の多くは住宅ローンを完済し、
持ち家比率が80%を超えるといわれます
(総務省「住宅・土地統計調査」)
資産としての“住まいの余力”を持つ層が増えているのです。
低金利時代に貯蓄を運用せず
家族への支援に回す傾向も強まっています。
子ども世帯の所得停滞と
住宅価格の上昇(平均4,700万円超)があり、
親の援助がなければ購入が難しい現実があります。
子どもに家を持たせたい・孫と近くに住みたい
という思いが資金支援の原動力となっています。
1-2 援助のかたちは「贈与」から「共同設計」へ
以前は資金を単純に贈与するケースが主流でしたが、
現在は建築計画への関与や
二世帯住宅への同居など、
家づくりそのものを共同で行うケースが増えています。
住宅ローン減税や相続時精算課税制度の活用により、
贈与税を抑えながら支援することも可能になりました。
制度の整備により親の資産を
相続後に分けるよりも生前に活かす流れが広がっています。
2-1 二世帯・近居の増加とその目的
二世帯・近居を選ぶ世帯は年々増加し、
全体の約17%に達しています。
目的として、最も多いのが
・親の老後の見守り(約40%)
・子育て支援(約28%)。
コロナ禍以降、リモートワークや在宅介護の増加もあり、
住宅を家族の支え合いの拠点として
再定義する動きが強まっています。
2-2 相続前支援
いま注目されているのが、相続前支援という考え方です。
相続発生後ではなく生前のうちに
家族で資産の使い方を考える取り組み
- 実家をリフォームして子世帯が住む
- 空き家になる前に売却し、資金を次世代住宅に充てる
- 家じまいを通じて相続対策を整理する
実家や親の家をどう活用するかを考えることが、
これからの時代の資産形成の第一歩です。
親からの援助で家を買う人が3人に1人。
家族の関係性を再設計する行動へと変化しています。
二世帯や近居、相続前支援など、
家を中心とした世代間のつながりは、
今後さらに重要になります。
家を残すではなく活かす。
意識の変化こそ、これからの住宅市場の主役です。
つづく
