こんにちはキャリーライフ中川です。
持ち家ギャップと相続の壁
総務省の「住宅・土地統計調査(2023年)」
全国の持ち家率は61.2%。
内訳を見ると世代間の格差が浮かび上がります。
65歳以上の高齢世代では持ち家率が約80%
30代以下の若年層では約40%
親が家を持ち、子が家を持たない。
相続と住まいの課題を複雑にしています。
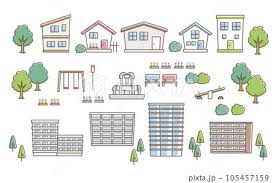
【目次】
1-1 親世代が築いた「持ち家社会」の功罪
1-2 若年層が家を持たない現実
2-1 二重資産がもたらす相続のリスク
2-2 実家を“未来資産”に変えるために
1-1 親世代が築いた「持ち家社会」の功罪
高度経済成長期以降、
持ち家を持つことが豊かさの象徴とされてきました。
・住宅ローン減税
・マイホーム給付金
・固定資産税軽減
政策的な支援もあり、
1990年代には持ち家率が
60%を超えて安定的に推移してきました。
多くは郊外や地方に建てられた住宅であり、
今もなお親世代が住み続けています。
問題は、その家を次に引き継ぐ子世代がいない、
または引き継がないケースが増えていることです。
1-2 若年層が家を持たない現実
2023年調査によると、30代以下の持ち家率は約40%
2013年時点の47%から7ポイント減少しました。
要因として
・賃貸志向の広がり
・共働き化による通勤立地の優先
・住宅価格の高騰
また、実家があるから急いで買わなくていい
という意識も影響しています。
親の持ち家があること自体が、
若年層の住宅取得意欲を抑制しているのです。
結果として、
家を持つ親・持たない子のギャップが広がり、
この差が相続時に問題となってきます。
2-1 二重資産がもたらす相続のリスク
親の家を含めて二重に不動産を所有すると、
相続時の調整が難しくなります。
特に兄弟姉妹間での分配や、
親の家を誰が引き継ぐかの話し合いが進まないまま、
空き家化・放置化するケースが増えています。
相続登記の義務化が始まったとはいえ、
全国で900万件以上の相続未登記不動産
残っているのが現状です(法務省調査)
実家を相続しても遠方に住んでいる場合、
維持管理や固定資産税の支払いが負担となり、
負動産化するリスクが高まります。
2-2 実家を“未来資産”に変えるために
持ち家ギャップを埋めるには、
家を残すではなく家をどう活かすか
という視点が欠かせません。
リフォームや賃貸活用、地域連携による再生など、
親の家を未来の資産として
再構築する動きが求められます。
家族間での住まい戦略を再構築する必要性があります。
つづく
