こんにちはキャリーライフ中川です。
ふるさと住民登録制度という
新しい仕組みが全国で広がりつつあります。
居住地とは別に、生まれ故郷や思い出の町など
もう一つの地域に登録できる制度です。
移住でも定住でもない、
関係人口として地域に関わる新しい形。
国の推計によると、
地方の人口は2045年に約2割減少。
一方で地域にもう一度つながりたいと 考える人が増えています。
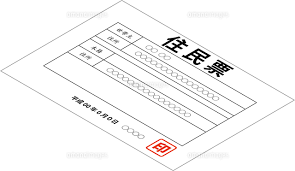
【目次】
1-1 制度の概要と目的
1-2 増える自治体導入の背景
2-1 「関係人口」という新しい概念
2-2 実家を持つ世代にこそ意味がある
1-1 制度の概要と目的
ふるさと住民登録制度は、
実際に居住していなくても、
希望する自治体に登録できる制度です。
住民票を移す必要はなく、登録すると
地域の行事・防災情報・活動案内を受け取れる仕組み。
導入を進めている自治体では、
地域貢献活動や空き家見学会への案内など、
登録者と地域のゆるやかなつながりを育てています。
総務省はこの仕組みを通じて、
移住ではなく関係づくりから始まる
地方創生を目指しています。
1-2 増える自治体導入の背景
全国で過疎化が進む中、
地方自治体の人口減少は深刻です。
総務省のデータによると、
2040年までに
全国の896自治体で人口が半減すると予測されています。
そうした中、観光やふるさと納税ではなく、
人の関わりを育てる制度として注目されているのが、
ふるさと住民登録です。
2024年時点で、全国50以上の自治体が試行導入を開始。
制度の目的は、地域の情報発信だけでなく、
・災害時の支援
・空き家活用
・地域ボランティアとの連携
実務的な協働にも及びます。
住んでいないけれど、つながっている
新しいふるさとの形を生み出しています。
2-1 「関係人口」という新しい概念
地方移住の次に注目されているのが関係人口です。
観光客や移住者ではなく、
地域に関わり続ける中間層。
総務省の調査によると、
関係人口の希望者は全国で約1,200万人(推計)。
中でも40〜60代は、
親の実家・相続・地域活動などを通じて関心が高い世代です。
ふるさと住民登録はきっかけを提供します。
年に1回の帰省やボランティアでも構いません。
関係を登録という形で可視化することで、
地域も個人も関わりの実感を持つことができます。
2-2 実家を持つ世代にこそ意味がある
実家が地方にあり、
将来的に空き家になるかもしれないと感じている人にとって、
ふるさと住民登録は
実家との距離を縮める第一歩になります。
登録を通じて自治体の情報を受け取り、
地域行事や住宅制度を知ることで、
家を守る準備や地域との接点が自然に生まれます。
また、将来的な帰郷・二拠点居住・地域貢献など、
選択肢を広げるきっかけにもなります。
「住む」ではなく「関わる」
今の時代に合った“ふるさととのつながり方”です。
地方が抱える課題をよそごとではなく、
自分ごととして考える。
実家や親の暮らしをきっかけに、
地域との関係を少しずつ取り戻す。
これからのふるさととの付き合い方なのかもしれません。
つづく
