こんにちはキャリーライフ中川です。
うちの町も、いずれなくなるかもしれない─
そんな言葉が現実味を帯びてきています。
日本創成会議が発表した最新の推計によると、
全国1741自治体のうち744(全体の約43%)が
消滅可能性自治体に該当します。
若年女性人口が将来半減し、
地域社会を維持できなくなる可能性が高いという指標です。
この数字は今後の住まい、資産、
家族の未来に直結する課題です。
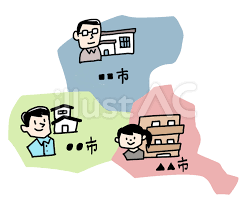
【目次】
1-1 「消滅可能性自治体」とは何か
1-2 全国744自治体という数値の意味
2-1 消滅可能性自治体が抱える“住まい・資産”のリスク
2-2 私たちができる備えと家との向き合い方
1-1 「消滅可能性自治体」とは何か
消滅可能性自治体とは、20〜39歳の女性人口が
2040年までに半分以下になる自治体を指します。
この年齢層は、
地域における出産・子育て世代にあたるため、
人口の再生産力の目安とされます。
内閣府の推計によれば、
全国的な人口減少率は2020〜2040年で約16%減ですが、
地方では40〜60%減に達する市町村も少なくありません。
地域によっては学校がなくなる、商店が閉じる
交通手段が消えるなど、
暮らしの基盤そのものが維持できなくなるのです。
1-2 全国744自治体という数値の意味
2024年版の分析によると、
消滅可能性自治体は全国の約4割。
中国・四国・九州地方では約6割が該当しています。
特に中山間地域では、
若年層の転出と高齢化が重なり、
町全体が限界集落化しているケースも見られます。
この現象は単なる人口問題ではなく、
・土地・家の資産価値
・地域の維持コスト
・相続後の処理
個人レベルの課題に直結します。
住まいの価値は立地だけでなく、
地域の継続性によっても決まる時代に入ったといえます。
2-1 消滅可能性自治体が抱える“住まい・資産”のリスク
人口が減る地域では、
住宅や土地の流動性が著しく低下します。
国土交通省の調査によると、
人口減少自治体の地価下落率は全国平均の約2倍。
相続した家を売ろうとしても買い手が見つからず、
・解体費用のほうが高い
・維持費が負担になる
相談が増えています。
公共インフラ(上下水道・道路・医療・介護施設)
維持が難しくなり、
住み続けられない家が増えるという現実もあります。
家は建っていても、地域が機能を失えば、
実質的な“空き家予備軍”となります。
住まいのリスクは、建物単体ではなく
地域単位で考える時代に変わりつつあります。
2-2 私たちができる備えと家との向き合い方
第一に重要なのは、地域の将来性を把握することです。
国土交通省の土地総合情報システムや、
総務省の人口動態統計などを活用すれば、
自分の実家・土地の属する自治体が、
今後どう変化していくのかを知ることができます。
第二に、早めの家族対話が欠かせません。
親世代が元気なうちに、
家をどうするか、地域に関わり続けるかを話し合う。
第三に、動かせる仕組みを持つこと。
家族信託や生前贈与、空き家バンクの活用など、
早めの手立てが将来の選択肢を広げます。
家を守るという発想から、家を活かすという発想へ。
消滅可能性自治体に生きる私たちに求められる姿勢です。
人口減少は止められなくても、関わり方は変えられます。
実家を見直す、地域に登録する、情報を共有する。
小さな行動の積み重ねが、
地域と家族の未来を支える力になります。
つづく
