こんにちはキャリーライフ中川です。
家余りが止まらないのか
総務省の「住宅・土地統計調査(2023年)」
全国の空き家数は900万戸に達し、
過去最多を更新しました。
空き家率は13.8%と最高水準。
人口が減る中で住宅数が増え続けるという
家余りの現実が広がっています。
空き家がここまで増えたのか
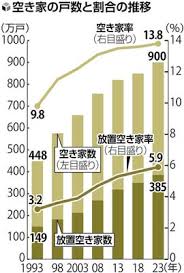
【目次】
1-1 人口減少と住宅供給のアンバランス
1-2 放置空き家がもたらすリスク
2-1 家を手放せない心理と制度の壁
2-2 「実家じまい」から始まる社会的課題解決
1-1 人口減少と住宅供給のアンバランス
30年間で日本の人口は約1,200万人減少
一方で住宅総数は増え続けています。
2023年の調査では住宅総数6,598万戸(前回比+79万戸)
人口よりも家が増えるという逆転現象が起きています。
特に、郊外や地方では高齢者が亡くなった後、
家を引き継ぐ人がいないケースが増加。
新築供給が止まらず、
使われない家が積み重なっていく構造が続いています。
1-2 放置空き家がもたらすリスク
900万戸の空き家のうち、
約350万戸はその他の住宅、
誰も住まず、賃貸も売却もされていない放置空き家です。
空き家は、倒壊リスク・火災・防犯・景観悪化など
地域課題を引き起こします。
築30年以上の老朽住宅では、
屋根や外壁の崩落が懸念され、
自治体の管理費用も年々増加しています。
空き家問題は、単なる不動産の話ではなく
地域の安全に関わる社会的テーマとなっています。
2-1 家を手放せない心理と制度の壁
なぜ所有者は家を手放せないのでしょうか。
背景には
・思い出が詰まっている
・親の遺志を守りたい
感情面の要素に加え、売却や相続手続きの複雑さがあります。
相続登記義務化が進んでいるとはいえ、
まだ相続未登記の土地・建物は
全国で約900万件(法務省推計)
解体費用や税制の仕組み
*更地にすると固定資産税が上がるなど
動かせない家・手放せない家が増え続けています。
2-2 「実家じまい」から始まる社会的課題解決
この現実を変える鍵は、家をどう引き継ぐか
家族で話すことです。
空き家問題は行政や不動産業界だけでなく、
家族一人ひとりの判断の積み重ねで変えられる課題です。
住まいを残すか手放すか
どちらも正解ですが、考えるタイミングが遅れると、
家は思い出から負担へと変わってしまいます。
想いを残し、家を活かすことこそ、
これからの空き家対策の本質です。
まずは自分の実家、親の家から。
家の未来を考えることが、
地域の未来を守る第一歩となります。
つづく
