こんにちはキャリーライフ中川です。
負動産から資源に変えるチャンスへ
総務省の「住宅・土地統計調査(2023年)」
全国の空き家のうち約7割が地方圏に集中しています。
過疎化や高齢化が進む地域では居住者が減る一方で、
空き家が増え続け、景観・防災
地域コミュニティに影響を及ぼしています。
近年、その空き家を地域の資源として
活かす動きが始まっています。
「空き家=問題」から「空き家=可能性」へ。
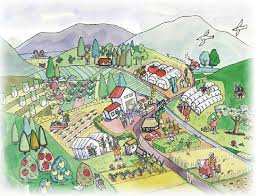
【目次】
1-1 地方に空き家が集中する理由
1-2 「使われない家」が地域に与える影響
2-1 空き家を再生する新たな動き
2-2 「住まいカイゼン」で地域の未来を守る
1-1 地方に空き家が集中する理由
2023年の調査によれば、空き家900万戸
うち約630万戸が地方部に所在しています。
要因は、人口減少と都市部への若年層流出です。
地方では子が地元を離れ、親が亡くなり、家が残る
という構図が定着しています。
交通の便が悪い、古い間取りで再販が難しいなど、
市場で流通しにくい滞留住宅が増えているのが現実です。
一方で、都市部では賃貸空き家の増加が中心。
1-2 「使われない家」が地域に与える影響
放置空き家の増加は、
単なる見た目の問題にとどまりません。
倒壊・火災・衛生・防犯といったリスクが高まり、
地域全体の地価を平均5〜10%下げるとの
試算もあります(国交省・空き家実態調査)
空き家が増えることで新たな移住者が住む余地を失い、
人口減少の悪循環を生むケースも多く見られます。
空き家は地域の老化を象徴するものでもあります。
2-1 空き家を再生する新たな動き
各地では空き家を地域資源として
再生する取り組みが進んでいます。
たとえば、
古民家を宿泊施設に改修するまち宿プロジェクト
地元の人と移住者が共に運営する
地域食堂・サテライトオフィスなど。
行政やNPOだけでなく、
民間企業や住民自らが手を動かす再生型モデルです。
特に2024年以降は、
国の地域活性化空き家再生事業により、
リノベーション費用の補助や
事業支援が拡充されつつあります。
手放された家が、新しい出会いの場へ
2-2 「住まいカイゼン」で地域の未来を守る
キャリーライフが提案する住まいカイゼンは、
単に建物を直すのではなく、
家族・地域・制度をつなぐ再生プロセスです。
空き家の背景には、必ず暮らしの記憶と
承継の途切れがあります。
整理し、リフォーム・利活用・売却など
最適な形へ導くことで、
空き家は“再び誰かの暮らしを支える場所に生まれ変わります。
地域資源としての家をどう活かすか。
その発想の転換が、これからの地方を救う鍵となります。
地方の空き家再生は、
単なる不動産ビジネスではなく、
人と土地をつなぎ直す社会的活動です。
家の再生が、地域の再生を生む時代が始まっています。
つづく
