こんにちはキャリーライフ中川です。
冬の乾燥、梅雨のじめじめ、夏の蒸し暑さ。
季節によって変わる湿度や空気の質は、
体調や睡眠の質に大きく関係しています。
厚生労働省の調査では、
室内湿度が40〜60%の範囲にあると最も健康的であり、
ウイルスの活動を抑え、
カビやダニの発生も防げると報告されています。
一方、換気不足や湿度の偏りが続く住宅では、
アレルギー症状や呼吸器疾患が2倍以上
増える傾向もあります。
見えない空気をどう整えるか健康住宅の鍵です。
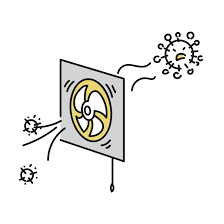
【目次】
1-1 湿度がもたらす健康への影響
1-2 カビ・ダニ・ウイルスのリスクを数字で知る
2-1 換気の仕組みが家の“呼吸”をつくる
2-2 空気を整える3つの習慣
1-1 湿度がもたらす健康への影響
湿度は、体感温度や快適性を左右するだけでなく、
健康状態にも直結します。
乾燥した空気は、のどや鼻の粘膜を弱らせ、
ウイルス感染を招きやすくします。
逆に、湿度が高すぎると
カビやダニが繁殖し、
ぜんそくやアトピーなどの原因になります。
厚生労働省によると、
湿度40〜60%が健康的な範囲。
この範囲を維持できている住宅では、
アレルギー性疾患の発症率が約30%低下
湿度の管理は快適のためではなく、
健康を守るための必須条件なのです。
1-2 カビ・ダニ・ウイルスのリスクを数字で知る
湿度と健康被害には、明確な相関があります。
たとえば、
カビは湿度70%を超えると急速に繁殖を始め、
ダニは湿度60%を超えると活動が活発化します。
一方で、インフルエンザウイルスは
湿度40%以下で生存率が2倍に
高まるという実験結果もあります。
乾燥しすぎても、湿気が多すぎても
健康リスクが増すのです。
見落とされがちなのが室内の二酸化炭素濃度。
厚労省の基準では1000ppm以下が
望ましいとされていますが、
換気が不十分な住宅では2000ppmを超えることも、
集中力低下や頭痛、倦怠感の原因になります。
2-1 換気の仕組みが家の“呼吸”をつくる
住宅の換気は、家の呼吸ともいえます。
日本の住宅では24時間換気が義務化されています。
実際には3割の家庭が常時換気を止めている
(環境省調査2024)という現実があります。
換気には
・第1種(機械で給気・排気)
・第2種(機械給気・自然排気)
・第3種(自然給気・機械排気)
3方式がありますが、
多くの住宅では第3種換気が採用され、
冬の冷気流入を避けるために
使用を止めてしまうケースが多いのです。
空気が入れ替わらない家は、
カビや結露、化学物質の滞留を招き、
住宅劣化と健康被害の両方を進行させる危険があります。
定期的なフィルター掃除と風の流れの確認が必要。
2-2 空気を整える3つの習慣
- 湿度40〜60%を維持する(加湿器・除湿器の併用)
- 1時間に1回以上の自然換気(窓を2か所開けて風を通す)
- 家具を壁から5cm以上離して結露を防ぐ
調湿効果のある建材(珪藻土・無垢材)を使うことも有効です。
近年では、二酸化炭素や湿度を
自動調整するスマート換気システムも普及し始めています。
空気の質をデザインする発想が、
これからの健康住宅のスタンダードになるでしょう。
人は一日に約2万回呼吸をします。
湿度と換気を整えることは、
薬や医療では得られない環境からの健康管理。
つづく
