こんにちはキャリーライフ中川です。
公的制度だけで足りる?
介護が必要になったら、介護保険があるから安心
そう思っていませんか?
介護保険でカバーできるのは
介護費用全体の半分以下というのが現実です。
要介護認定を受けても、
利用限度額や自己負担の上限があり、
公的制度だけでは十分な
介護を受けられないケースが増えています。
長寿化が進む中で、介護費用をどう確保するかが
これからの世代共通の課題になっています。
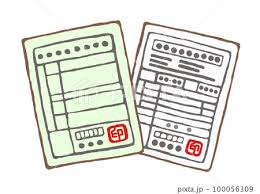
【目次】
1-1 公的介護保険の仕組みと限界
1-2 「要介護2以上」からが支給対象という現実
2-1 平均介護期間と費用の実態
2-2 介護に備えるための現実的な選択
1-1 公的介護保険の仕組みと限界
介護保険制度は2000年にスタートし、
40歳以上の全国民が加入する
仕組みとして運用されています。
要介護認定を受けると、
介護サービス利用時の自己負担は原則1〜3割。
支給には要介護度ごとに
月ごとの利用限度額が設定されています。
たとえば
要介護3でも、上限を超えたサービスは全額自己負担。
生活支援・家事援助・通院付き添いなど、
実際の暮らしに必要な部分は制度外となるケースが多く、
制度の枠を超えた部分にこそ家計負担が集中しています。
1-2 「要介護2以上」からが支給対象という現実
多くの人が誤解しているのが、支給対象の範囲です。
実際には、要支援1・2や軽度の要介護1では、
受けられるサービスの種類・回数が
大きく制限されています。
訪問介護やデイサービスの利用も回数制限があり、
在宅での生活を維持するには自費負担が不可避です。
厚生労働省のデータでは、
介護が必要になった人の約4割が
要支援・要介護1の段階で支出に悩んでいます。
この軽度介護期の支援不足が、
家族の介護負担を重くしている要因です。
軽い段階からの支援がなければ、
重度化を防げないという指摘もあります。
2-1 平均介護期間と費用の実態
内閣府「高齢社会白書(2024年)」によると、
介護が始まってから亡くなるまでの平均期間は
男性4.5年・女性6.9年
その間にかかる介護費用の総額は、
生命保険文化センターの調査で
一人あたり約550万円とされています。
公的保険で補えるのはそのうちおよそ230万円前後。
残り300万円以上は自己負担ということです。
また、介護にかかわる家族の離職も深刻で、
年間約10万人が介護離職を余儀なくされています。
経済・時間・精神の3つの負担が重なるのが介護の現実です。
2-2 介護に備えるための現実的な選択
介護費用に備える方法は、
公的制度だけでは限界があります。
最近では民間の介護保険や就業不能保険を利用して、
将来の介護期間に備える人が増えています。
特に、40代・50代での早期加入が有利とされ、
介護発生時に毎月一定額の給付を受けられるタイプが人気です。
親の介護だけでなく自分の介護に備える考え方も広がっています。
国が推奨する“自助・共助・公助”のバランスを取るためには、
自分で選ぶ介護費用の確保が欠かせません。
保険を負担ではなく、生活を支える仕組みとして
捉えることが、これからの備え方です。
制度がある=安心ではなく、
制度の外をどう支えるかが問われる時代。
つづく
