こんにちはキャリーライフ中川です。
昔は家を持つことは人生の目標とされてきました。
近年は、若い世代を中心にその考え方が変わってきています。
世代ごとの持ち家率を比較すると、
ライフスタイルや社会背景の違いが見えてきます。
住まいをめぐる現実をお伝えします。
【目次】
1-1 30代・40代の持ち家率は下がっている
1-2 50代・60代は依然として高水準
2-1 国際比較でみる日本の持ち家率
2-2 少子高齢化と住宅ストックの増加
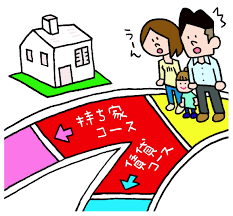
- 30代・40代の持ち家率は下がっている
国土交通省の「住宅・土地統計調査」によると、
30代前半の持ち家率は
1990年代には50%近くありましたが、
直近では40%を切っています。
40代でもかつては70%近かった水準が
60%台前半まで下がりました。
背景には、雇用の不安定化や結婚年齢の上昇があります。
正規雇用比率の低下や非正規雇用の増加により、
住宅ローンを組む自信が持てない世帯が
増えたことが大きな要因です。
1-2 50代・60代は依然として高水準
50代後半から60代の持ち家率は80%を超えています。
高度経済成長期やバブル期に住宅を購入した層が中心であり、
ローンを完済した人も多い世代です。
高齢者世帯は家を持っているが、子世代は持っていない
二極化が進んでいます。
相続時に空き家が残る構図を生みやすい要因になります。
2-1 国際比較でみる日本の持ち家率
日本全体の持ち家率は約60%台後半で推移しています。
ドイツ(約50%)、イギリスやアメリカ(約65〜70%
日本は親の持ち家を相続するケースが多く、
世代間で住宅資産の偏りが大きいのが特徴です。
相続を前提とした持ち家社会は、
今後の空き家増加を加速させる懸念があります。
2-2 少子高齢化と住宅ストックの増加
日本は人口減少により住宅が余り始めています。
総務省の統計では、
すでに住宅総数は世帯数を上回り、
空き家は900万戸に達しました。
少子化で住宅需要が減る一方で、
持ち家は増え続けてきたため、
需給のバランスが崩れています。
家を持っても将来子どもが住まないという現実が、
実家じまいを考えるきっかけになっているのです。
つづく
